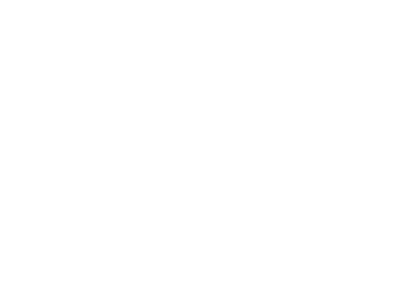シキミ(№612)
山間部では雪の残る3月、つやのある常緑の葉をつけた小高木が黄白色の花を開いています。マツブサ科シキミ属のシキミです。花の少ないこの時期、目立つ花木の一つと言えるでしょう。シキビ、ハナノキ、ハナシバ、ハカバナ、ブツゼンソウなど多くの別名で呼ばれ、昔から仏事や神事に用いられてきた身近な植物です。
樹高2~10mの常緑樹で、3~4月、枝の先端に直径2、5~3㎝で黄白色の花を数個まとめて付けます。花弁とがくは区別しにくく、花被片として12~28枚がらせん状につきます。9~10月に8角形で2~3cmの星状果実をつけ、乾燥して木質化すると種子を弾き飛ばします。この果実はアニサチンなどの有毒物質を含み、「毒物劇物取締法」で植物としては唯一劇物に指定されている有毒植物です。
この果実に酷似した香辛料にハッカク(スターアニス)があります。これは日本には自生しないトウシキミの果実で非常によく似ていますが、ハッカクは甘い香り、大きさがやや大きい(3~4cm)、星の先端が丸みを帯びるなどの点で区別できます。
シキミは有毒植物で、動物の食害を受けにくいと言われていますが、食害する昆虫がいて、シキミタマバエが葉にチュウエイ(ゴール)を作りますし、食害中の鱗翅目幼虫も見られました。
(*画像をクリックすると拡大されます)
樹高2~10mの常緑樹で、3~4月、枝の先端に直径2、5~3㎝で黄白色の花を数個まとめて付けます。花弁とがくは区別しにくく、花被片として12~28枚がらせん状につきます。9~10月に8角形で2~3cmの星状果実をつけ、乾燥して木質化すると種子を弾き飛ばします。この果実はアニサチンなどの有毒物質を含み、「毒物劇物取締法」で植物としては唯一劇物に指定されている有毒植物です。
この果実に酷似した香辛料にハッカク(スターアニス)があります。これは日本には自生しないトウシキミの果実で非常によく似ていますが、ハッカクは甘い香り、大きさがやや大きい(3~4cm)、星の先端が丸みを帯びるなどの点で区別できます。
シキミは有毒植物で、動物の食害を受けにくいと言われていますが、食害する昆虫がいて、シキミタマバエが葉にチュウエイ(ゴール)を作りますし、食害中の鱗翅目幼虫も見られました。
(*画像をクリックすると拡大されます)
homeへ
キアシシギ(№611)
日本の春と秋に姿を見せるチドリ目シギ科のキアシシギです。冬は東南アジアやオーストラリアで越冬し、夏にはシベリア、カムチャッカ半島などで繁殖する旅鳥です。
全長25cm程度の中型種で、背面全体が灰褐色で翼、腰などに目だった模様がないのが特徴です。胸や脇には細かい褐色横班があります。目の周りには白いアイリング、黒い過眼線(嘴の付け根から目を通る帯)があります。嘴は黒く、基部が灰黄色で真っすぐ、脚は黄色です。
海岸の砂浜、干潟、磯、水田などで普通にみられ、カニ、ゴカイ、貝、昆虫などを食べています。海沿いでは防波堤やテトラの上などで休む姿がよく見られましたが最近、京都、大阪では飛来数が減少し、滋賀県では希少種となっているようです。
(*画像をクリックすると拡大されます)
全長25cm程度の中型種で、背面全体が灰褐色で翼、腰などに目だった模様がないのが特徴です。胸や脇には細かい褐色横班があります。目の周りには白いアイリング、黒い過眼線(嘴の付け根から目を通る帯)があります。嘴は黒く、基部が灰黄色で真っすぐ、脚は黄色です。
海岸の砂浜、干潟、磯、水田などで普通にみられ、カニ、ゴカイ、貝、昆虫などを食べています。海沿いでは防波堤やテトラの上などで休む姿がよく見られましたが最近、京都、大阪では飛来数が減少し、滋賀県では希少種となっているようです。
(*画像をクリックすると拡大されます)
homeへ
ノシラン(№610)
秋から冬にかけ、暖地の海岸沿林地を歩くと、コバルトブルーの実をつけ、長さ30~80cm、幅が5~15mmの細長い葉を叢生した下草を見ることがあります。
これは、キジカクシ科ジャノヒゲ属のノシランです。常緑性で7~9月に直径1~2㎝の白色、漏斗型花冠を持った花を多数房状に着けます。この花の花茎は傾斜し、のちに種皮が早くに脱落しむき出しになった種子を付けます。リュウノヒゲ(タマリュウ)(№317)を大型にしたような植物です。常緑で、種子がコバルトブルーと美しいため、和風庭園の下草として利用されることもあります。ノシランの地下茎は匍匐茎とならず下に向かって伸びるため横に広がらずに大株となります。学名をOphio(蛇)pogon(ひげ) jaburan(ヤブラン)と言い、日本語を直訳した名前になっています。
これに非常によく似た植物にヤブラン(№101)があります。ヤブランはキジカクシ科ヤブラン属で花の色は桃色~紫で花茎は直立します。また、実(種子)は黒紫色で、斑入りの園芸種フイリヤブランは街路や公園などでよく見かけます。
(*画像をクリックすると拡大されます)
これは、キジカクシ科ジャノヒゲ属のノシランです。常緑性で7~9月に直径1~2㎝の白色、漏斗型花冠を持った花を多数房状に着けます。この花の花茎は傾斜し、のちに種皮が早くに脱落しむき出しになった種子を付けます。リュウノヒゲ(タマリュウ)(№317)を大型にしたような植物です。常緑で、種子がコバルトブルーと美しいため、和風庭園の下草として利用されることもあります。ノシランの地下茎は匍匐茎とならず下に向かって伸びるため横に広がらずに大株となります。学名をOphio(蛇)pogon(ひげ) jaburan(ヤブラン)と言い、日本語を直訳した名前になっています。
これに非常によく似た植物にヤブラン(№101)があります。ヤブランはキジカクシ科ヤブラン属で花の色は桃色~紫で花茎は直立します。また、実(種子)は黒紫色で、斑入りの園芸種フイリヤブランは街路や公園などでよく見かけます。
(*画像をクリックすると拡大されます)